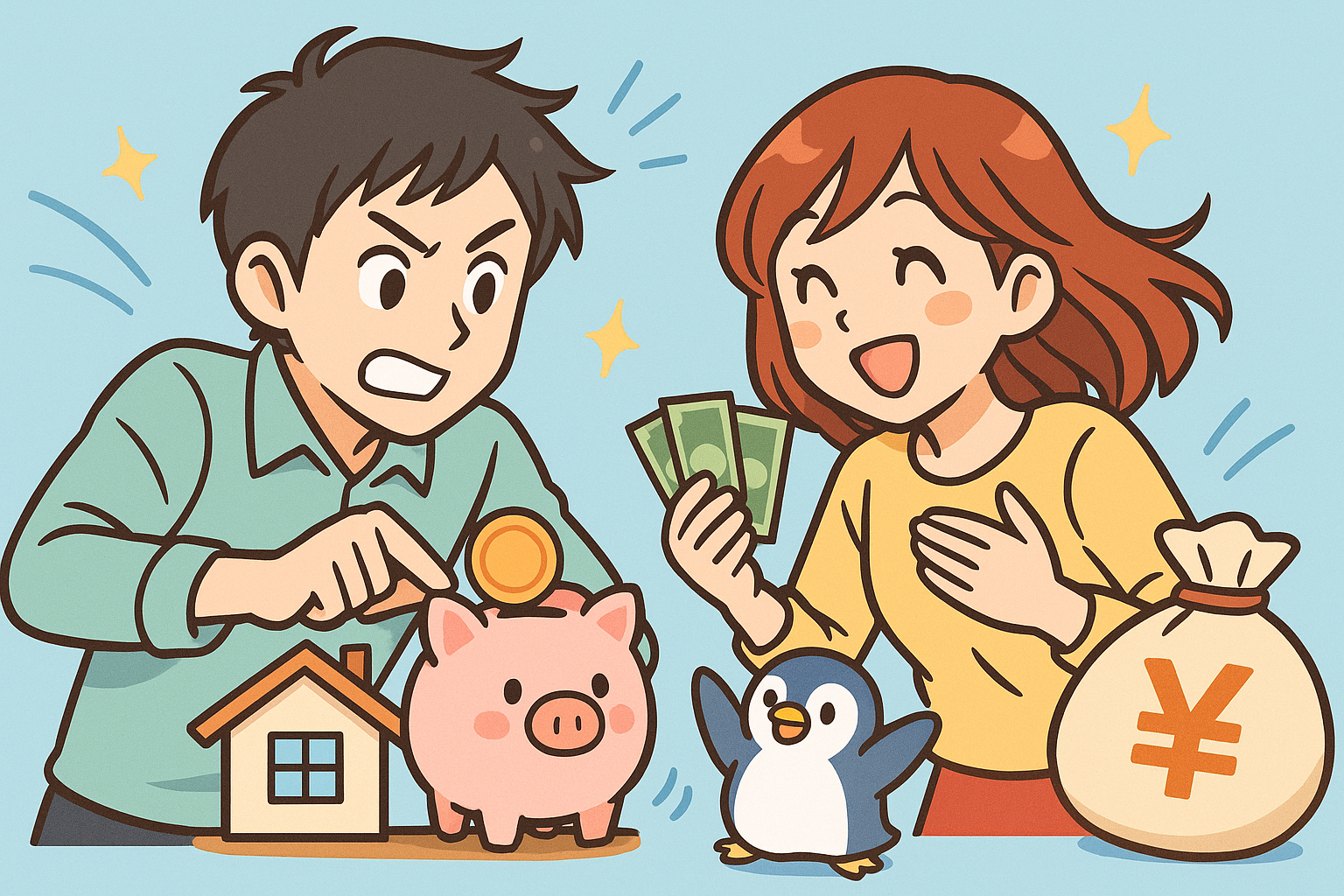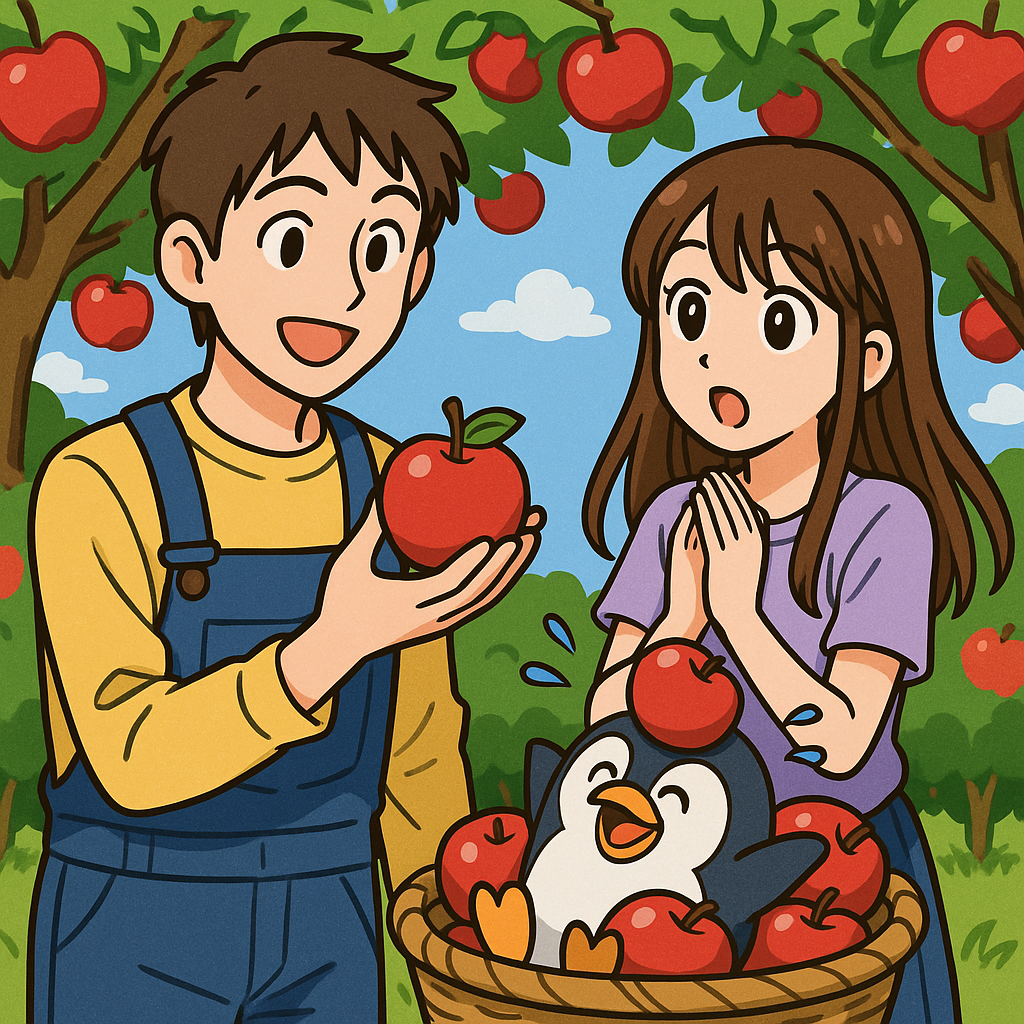👨シュンタ「教育費って、思ってるよりずっと大きいんだよな」
💁♀️カオリ「でも、今から準備すれば“足りる未来”にできるよ」
子どもが大学進学を迎えるその日、安心して「行ってらっしゃい」と送り出せるように。
この記事では、教育費の総額・貯め方・運用法を3ステップで整理します
🟢 STEP 1|基礎を知る
国公立・私立、自宅・下宿別の費用を把握する
🟠 STEP 2|準備を始める
児童手当・新NISA・現金積立を組み合わせる
🔵 STEP 3|家計全体で支える
保険や固定費を整えて積立余力を作る
我が家の実例や積立データも交え、読み終えた瞬間から動き出せる実践ガイドにしました。
🟢STEP1|基礎を知る
💡 まずは「いくら必要か」を把握
国公立か私立か、自宅か下宿かで総額は大きく変わります。
自宅なら約700〜900万円、下宿なら約1,000〜1,200万円が目安。我が家も最初にこの数字を見たときは「奨学金なしは無理」と思いましたが、必要額を正確に知ることで逆算して計画を立てられました。
大学進学パターン別・総額(4年間)
| 進学パターン | 内訳(授業料+生活費) | 総額(4年間) |
|---|---|---|
| 国公立・自宅 | 約240万円+約480万円 | 約720万円 |
| 国公立・下宿 | 約240万円+約760万円 | 約1,000万円 |
| 私立・自宅 | 約400万円+約480万円 | 約880万円 |
| 私立・下宿 | 約400万円+約760万円 | 約1,160万円 |
👨シュンタ「うちは子ども2人だから、国公立・自宅でも1,400万円かかる計算なんだよな」
💁♀️カオリ「でも児童手当で約400万円はカバーできるから、残り1,000万円をどう作るかがポイントだね」
✏️
我が家の場合はこの数字ですが、必要な金額は家庭によって大きく変わります。
子どもの人数、国公立か私立か、自宅通いか下宿か──この組み合わせ次第で、何百万円も差が出ます。
まずは、現状を整理してみましょう。
✅ 【STEP1】教育費チェックリスト
- 教育費総額を試算した
- 国公立・私立・下宿別の費用差を把握した
- 児童手当の累計額を計算した
💡 こちらでさらに詳しく
- 📚 塾代はいくらかかる?|中学・高校別の年間コストと上限目安
→ 月謝・年間費用・上限ラインを整理。塾代が教育費全体にどう影響するかが分かる。 - 🎓 【PR】大学進学にいくらかかる?費用まとめとリアルな対策
→ 国公立・私立、自宅・下宿別の費用差と、足りない分をどう準備するかを解説。 - 🎓 教育費っていくらかかる?平均額と我が家の準備ロードマップ
→ 教育費の全体像と、家庭ごとの違いを把握する入口記事。
🟠STEP2|準備を始める
💡 少額でも早く始めれば、後半の負担は大幅減
教育費は「少しずつでも早く準備を始める」ことで、後半の家計負担を大きく減らせます。
まずは児童手当を全額貯める専用口座を作り、生活費と混ざらない仕組みを整えましょう。
不足分は新NISAや定期預金で補い、投資は18歳までの長期を前提に、現金枠も確保しておくのが安心です。
📊 児童手当+積立のカバー率シミュレーション(1人あたり)
| 準備方法 | 想定額 | カバー率(国公立・自宅) |
|---|---|---|
| 児童手当全額貯蓄 | 200万 | 約28% |
| 新NISA 年額24万円積立 (18年・年利3%想定) |
約560万 | 約80% |
| 現金定期預金 年額10万円積立(18年) | 180万 | 約26% |
💡 合計で約940万円 → 国公立・自宅ならほぼカバー可能
👨シュンタ「うちは児童手当は全額、専用口座に入れて手を付けないようにしてる」
💁♀️カオリ「NISAは教育費用と老後用に分けて積み立ててるよ」
🤖ピー助「必要な時期が決まってる分は、ちゃんと現金で確保してるでぴ!」
✏️
教育費の準備は、この3つを押さえておけばまず安心です。
ここまでの流れを、自分の家でもできているかチェックしてみましょう。
✅ 【STEP2】準備チェックリスト
- 児童手当専用口座を作った
- 教育費積立を生活費と分けた
- 新NISAや現金積立で長期準備を始めた
💡 さらに知っておきたい教育費の選択肢
- 📊 大学入学資金の準備は現金と積立どっち?|ベストな方法を比較
→ まとまった資金を「どう用意するか」を判断できる。 - 💰 児童手当って全部つかっていいの?我が家のリアルな使い方
→ 教育資金として貯めるための現実的な工夫。 - 📈 教育費に新NISAってアリ?わけて積み立てる我が家の考え方
→ 教育費と投資を組み合わせた積立戦略。 - 🏦 教育資金贈与は非課税で最大1,500万円|祖父母から孫への支援制度を3STEPで解説
→ 制度を活用して大きな支援を受けられる方法。
🔵STEP3|家計全体で支える
💡 教育費単独では貯めにくい。家計全体のバランス調整がカギ
教育費は単独で貯めるより、家計全体を整えて余力を作るほうが効率的です。
保険の見直しや通信費の削減などの固定費スリム化で毎月1〜3万円の余力を作れば、18年で数百万円の差になります。
浮いたお金は教育費専用口座に自動振替して、無理なく積立を続けましょう。
📊 固定費見直しの効果(我が家の例)
| 項目 | 見直し前 | 見直し後 | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 生命保険 | 15,000円 | 6,000円 | 108,000円 |
| 通信費(夫婦) | 12,000円 | 6,000円 | 72,000円 |
| サブスク | 8,000円 | 5,000円 | 36,000円 |
| 合計 | – | – | 216,000円 |
💡 年間約21.6万円削減 × 18年 = 約390万円 → 教育費資金の加速装置に
👨シュンタ「保険は必要な保障だけ残して整理した」
💁♀️カオリ「通信費は格安プランに変更したよ」
🤖ピー助「浮いた分は毎月ちゃんと教育費口座に移動してるでぴ!」
教育費を加速させるには、まずこの3つを押さえておくと安心です。
ここまでの流れを、自分の家でもできているかチェックしてみましょう。
✅ 【STEP3】家計見直しチェックリスト
- 保険契約を一覧化して不要な保障を確認した
- 通信費・サブスクを見直した
- 浮いたお金を教育費口座に自動振替している
💡 教育費を支える“家計の整え方”もチェック
- 🎯 資産形成の設計図|教育費・住宅・老後をぜんぶ叶える“5つのSTEP”
→ 目的別に優先順位を整理し、暮らし・貯蓄・投資を組み合わせて最適化する方法を解説。 - 🏠 夫婦で家計どうやって見てる?我が家の“ざっくり家計管理法”
→ 固定費を整えて教育費の原資を作る方法。 - 🛡️ 保険見直しで教育費を作る方法
→ 不要な保険を減らして必要な保障は残すコツ。 - 🏠 教育費と住宅ローンの両立|破綻しない家計配分の考え方
→ 住宅費と教育費を同時に抱えるときの戦略。 - ⏰ 教育費のピークはいつ?|家計が崩れやすい時期の乗り切り方
→ 集中期の負担をどう乗り切るかを解説。
ケーススタディ|FP相談で削減額を積立に回したら…
💬 相談前の我が家の悩み
- 教育費は児童手当+NISAで準備していたが、追加積立の余力がない
- 保険・通信費・サブスクなどの固定費が高止まりしていた
- どこから削ればいいか、優先順位がわからなかった
このとき試したのが、「削減できた分をそのまま教育費に積み立てる」というシミュレーションです。
どれくらい貯まるのかを見てみましょう。
📊 削減額をそのまま18年間積み立てた場合(年利3%想定)
| 項目 | 毎月の追加積立額 | 18年後の総額 |
|---|---|---|
| 保険見直し分 | 9,000円 | 約230万円 |
| 通信費見直し分 | 6,000円 | 約150万円 |
| サブスク見直し分 | 3,000円 | 約77万円 |
| 合計 | 18,000円 | 約457万円 |
💡 児童手当(約200万円)+既存積立と合わせれば、国公立・自宅進学費用はほぼカバー可能に!
💁♀️カオリ「削減額を“消費”じゃなくて“積立”に回すだけで、こんなに差が出るんだ」
🤖ピー助「FPなら“どこから削ってどこに回すか”まで見てくれるでぴ!」
まとめ|教育費を“借金なし”で乗り切るために
→国公立・私立、自宅・下宿別の費用を把握する
→児童手当・新NISA・現金積立を組み合わせる
→保険や固定費を整えて積立余力を作る
👨シュンタ「結局、“早く・仕組み化・バランス”がカギだな」
💁♀️カオリ「今やれば、子どもに借金を背負わせずに済むはず」
🤖ピー助「未来の学費は“今の習慣”で変わるでぴ!」
🧭 関連記事でもっと準備を進める
💁♀️カオリ「もっと細かいテーマも押さえておくと安心だよ」
🤖ピー助「関心がある人だけ深掘りできるようにするでぴ!」
💰 家計とお金の工夫

📚 制度・仕組みを活用する
🎓 奨学金・保険の選択


🤔 意識と行動の違い
📌 次の一歩
教育費と老後資金は同時に準備しないと、どちらかが犠牲になりがちです。
次は「教育費と老後資金の両立戦略」をチェックして、家計全体を最適化しましょう。
➡️ 資産形成まとめ|教育費・老後・投資のバランスを取る方法
資産運用、始め方に迷ってますか?
我が家の投資スタイルと運用戦略をまとめました。