💁♀️カオリ「子どもの教育費ってどう準備する?って話になると、必ず“学資保険”が出てくるよね」
🧔♂️シュンタ「でも実際に調べたら、“安心料が高すぎる”って結論になったんだよな」
🤖ピー助「なんとなく安心に見えて、実は“自由を奪う罠”でぴ!」
✍️
子どもが生まれると、周りから「学資保険は入っておいた方がいいよ」と言われることが多い。
確かに“元本保証”や“返戻率108%”といった安心感はあるけど――。
- 年0.7%程度の利回りしかない
- 途中解約で元本割れのリスク
- 家計の変化に柔軟に対応できない
これらを冷静に考えた結果、我が家は「入らない」という決断をしました。
その代わりに、児童手当+NISA+現金積立という3本柱で、学資保険よりも自由度が高く、結果的により確実な教育資金準備を進めています。
🧔♂️シュンタ「“安心を買う”んじゃなく、“仕組みで作る”。これがうちの答えだな」
💁♀️カオリ「数字で見ても、学資保険より現実的だと思う」
👉 この記事を読むとわかること
- 実際にどれくらい貯まるのか、具体的な数字シミュレーション
- なぜ我が家が学資保険を選ばなかったのか
- 学資保険の代わりに使っている「3つの現実的ルート」
学資保険、やっぱり“合わなかった”わが家の判断
💁♀️カオリ「なんで最初から“入らない”って決めたんだっけ?」
🧔♂️シュンタ「理由はシンプル。“安心料が高すぎた”から。」
✍️ 学資保険をシミュレーションするとこうなります👇
- 利回りが低すぎる
例:返戻率108%、15年払い込みで200万円 → 216万円に。
→ 年利換算すると0.7%前後。
→ 一方で、つみたてNISAで年3%運用できれば15年で約250万円に。差額は30万円以上。 - 途中解約リスク
子どもが小さいうちは急な出費も多い。
でも学資保険は「10年未満で解約=元本割れ」になりやすい。
→ “必要なときに使えない”って、教育資金なのに本末転倒。 - 柔軟性がない
毎月決まった額を15年〜18年払い続けなきゃいけない。
→ 収入減・転職・2人目誕生など、家計が変わっても調整できない。
→ NISAや現金積立なら「一時停止」や「額の調整」が自由にできる。
🧔♂️シュンタ「要するに、“安心を買ってるつもりで、自由とリターンを失ってる”ってことだな」
💁♀️カオリ「うちの場合、それが“逆に危険”だったんだよね」
🤖ピー助「“安心して損する”って、一番高い授業料でぴ!」
「じゃあどうする?」わが家が選んだ3つの現実的ルート
🧔♂️シュンタ「学資保険に入らないなら、その“安心”はどう作る?」
💁♀️カオリ「うちは、3つの手段を組み合わせることにしたよ」
🤖ピー助「“保険ナシ=無防備”じゃなく、“別ルートで守る”ってことでぴ!」
✍️
わが家の教育資金対策は、この 3本柱 で回しています👇
- 💰 児童手当は“自動貯金”扱い
→ 受け取ったら即、専用口座に避難。15年で約200万円の土台をつくる。 - 📈 NISAでちょいアシスト
→ 教育費を“全部投資”にはしない。余力分だけを長期で運用。 - 🏦 現金積立で最終ライン確保
→ 必要なタイミングで絶対確保できるように、別口座で現金をストック。
🧔♂️シュンタ「この3つを組み合わせれば、“増やすより確実に届かせる”ができる」
💁♀️カオリ「安心を買うんじゃなく、仕組みで作るって発想だね」
🤖ピー助「保険の代わりに“3種の神器”を揃えたってことでぴ!」
代替策①:児童手当は“自動貯金”と割り切る
🧔♂️シュンタ「児童手当って、子どもの“おこづかい”じゃなくて教育資金のタネ銭だよな」
💁♀️カオリ「もらった瞬間に“貯金扱い”にするのが鉄則だね」
✍️
わが家では、児童手当は生活費と完全に切り離して“教育費専用口座”に即避難。
使わないルールを徹底するだけで、これだけ積み上がります👇
- 毎月1.5万円(3歳〜中学卒業まで15年間)
- 年間18万円 × 15年 = 約200万円
💁♀️カオリ「0円から200万が“自動で貯まる”って冷静に考えるとすごいよね」
🤖ピー助「“使わない勇気”が最強の節約術でぴ!」
📌 じゃあ「手を付けない仕組み」としては、学資保険の方が安心なんじゃ?
→ そう思う人も多いけど、そこが落とし穴。
- 学資保険は確かに“強制力”はある
- でも「収入減ったから一時的に減らしたい」と思ってもできない
- 解約すると元本割れリスクあり
🧔♂️シュンタ「つまり“使えない安心”を買ってる感じなんだよな」
💁♀️カオリ「その点、児童手当+専用口座なら、必要なときは下ろせる。柔軟さが全然違うよ」
🤖ピー助「“安心のために不自由になる”か、“仕組みで自由に守る”かの違いでぴ!」
代替策②:NISAで少しアシストをかける
💁♀️カオリ「投資って怖いけど…“短期で使わないお金”ならアリかもね」
🧔♂️シュンタ「うちは教育費の全部じゃなくて、一部をNISAで運用してる。あくまで“アシスト役”としてな」
✍️
NISAは“教育費を増やす魔法”ではなく“ちょい足しのサポート”という位置づけ。
現金と児童手当がベースにあるからこそ、余力で投資できる。
📌 我が家のルールはシンプル👇
- 必要時期の3年前には現金化
→ 高校・大学の入学直前に暴落すると致命的。だから「使う時期の3年前」からは守りに入る。 - 教育費のメインにはしない(アシスト役)
→ 「全部NISAでまかなう」なんて無謀はしない。あくまで補助。 - 投資は“余力資金”からのみ
→ 家計に余裕があるときだけ。生活費や防衛資金には絶対に手を出さない。
🧮 例えば:毎月2万円を18年間つみたてると――
- 元本:約430万円になるので・・・
年3〜4%で運用できれば 600万円超
→ 預金だけでは届かない部分を、長期の複利で“底上げ”できる。
🤖ピー助「“全力投資でワンパン狙う”んじゃなく、“バフかけて堅実プレイ”ってことでぴ」
代替策③:現金積立で“期日までの確保”を優先
🧔♂️シュンタ「いくら投資で増やしても、タイミング悪ければ一瞬で消えるからな」
💁♀️カオリ「だから最後の仕上げは“現金”。これが一番の安心だよね」
✍️
教育費のゴールは「必要な時に、必要な額が確実にあること」。
そのために、わが家では“現金積立”を最終ラインとして設定しています。
📌 わが家の仕組み👇
- 児童手当とは別に、月1〜2万円を積立
→ 金額は無理のない範囲でOK。たとえ月5,000円でも、18年で約100万円近くになる。 - 夏・冬のボーナスから年間数万円を追加
→ 余裕があるときだけ上乗せするスタイル。定期預金やつみたて定期に振り分けて「必ず残す仕組み」に。 - 生活防衛資金とは分ける
→ 教育費は教育費、生活費は生活費。財布を分けるだけでメンタルも安定する。
💡 ポイントは「金額」より「仕組み」。
余力がある月は多めに、厳しい月は少なくてもいい。とにかく“ゼロにしない”ことが積み上がりにつながります。
💁♀️カオリ「“最悪これだけはある”って現金があると、進学の時に迷わなくて済む」
🤖ピー助「額の大小より、“現金シールド”があるかどうかで安心感が全然違うでぴ!」
まとめ:「増やす」より「届かせる」がわが家の戦略
✍️
学資保険は悪ではありません。
でも、我が家は「自由度と効率」を重視して、別の3本柱を選びました。
【📌 わが家の戦略まとめ】
- 児童手当 → 使わずストックで約200万円
- NISA → 余力で運用し、長期で数百万円の“ちょい足し”
- 現金積立 → 無理のない範囲で“最終ライン”を確保
合計すれば、18年で数百万円〜1,000万円規模の教育資金を準備できる見込み。
「安心」を保険で買うのではなく、仕組みで作れることがわかります。
💁♀️カオリ「結局コツコツが一番なんだよね」
🧔♂️シュンタ「派手な裏技より、地道に積んだほうが勝ちだな」
🤖ピー助「でも僕は宝くじ当たる派でぴ!」
🎓 関連記事でさらに詳しく
🤖ピー助「教育費まわりの全体像がわかる関連記事、こっちで揃えるでぴ!」
- 🎓 教育費っていくらかかる?平均額と準備ロードマップ
→ 公立・私立別の費用目安と準備スケジュールを解説。 - 💵 児童手当って全部使っていい?“ガチ会議”の末に我が家が出した答え
→ 「貯める?使う?」迷ったときのリアルな判断と会議の記録。 - 📈 教育費にNISAでアシストかけて乗り切る工夫、集めました
→ 預金だけじゃ不安…投資をどう組み合わせれば安心できるかを整理。 - 📊 教育資金、家、老後…全部やりたい!資金どう配分してる?
→ 全取り思考の資金設計を、我が家の実例でシミュレーション。 - 🏠 住宅ローン、フルローンってアリ?我が家の“試算と相談”までのリアル【PR】
→ 教育費との両立を考えたときの住宅ローン戦略の一例。
未来の学費が不安ですか?
我が家の準備法とロードマップをまとめました。
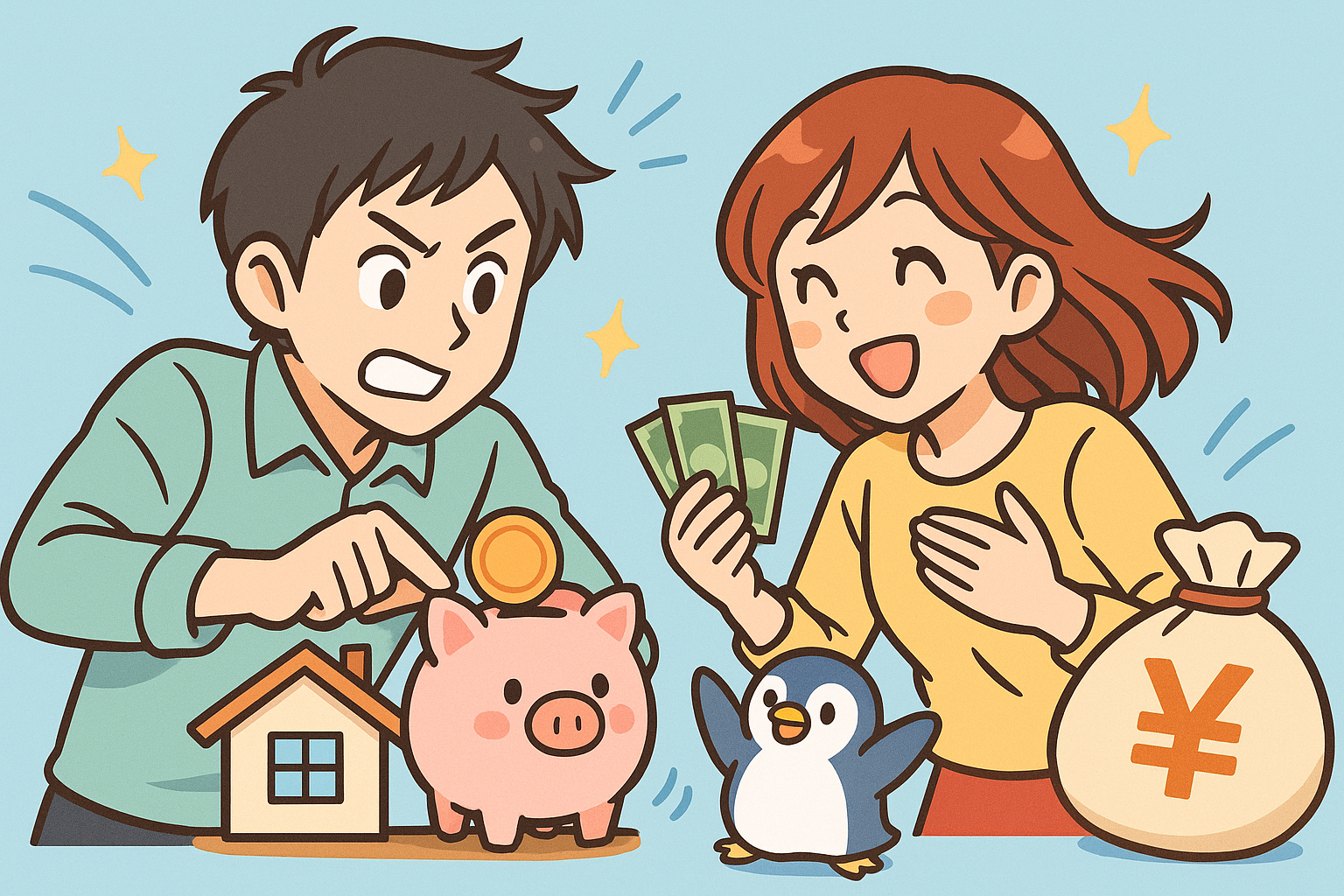






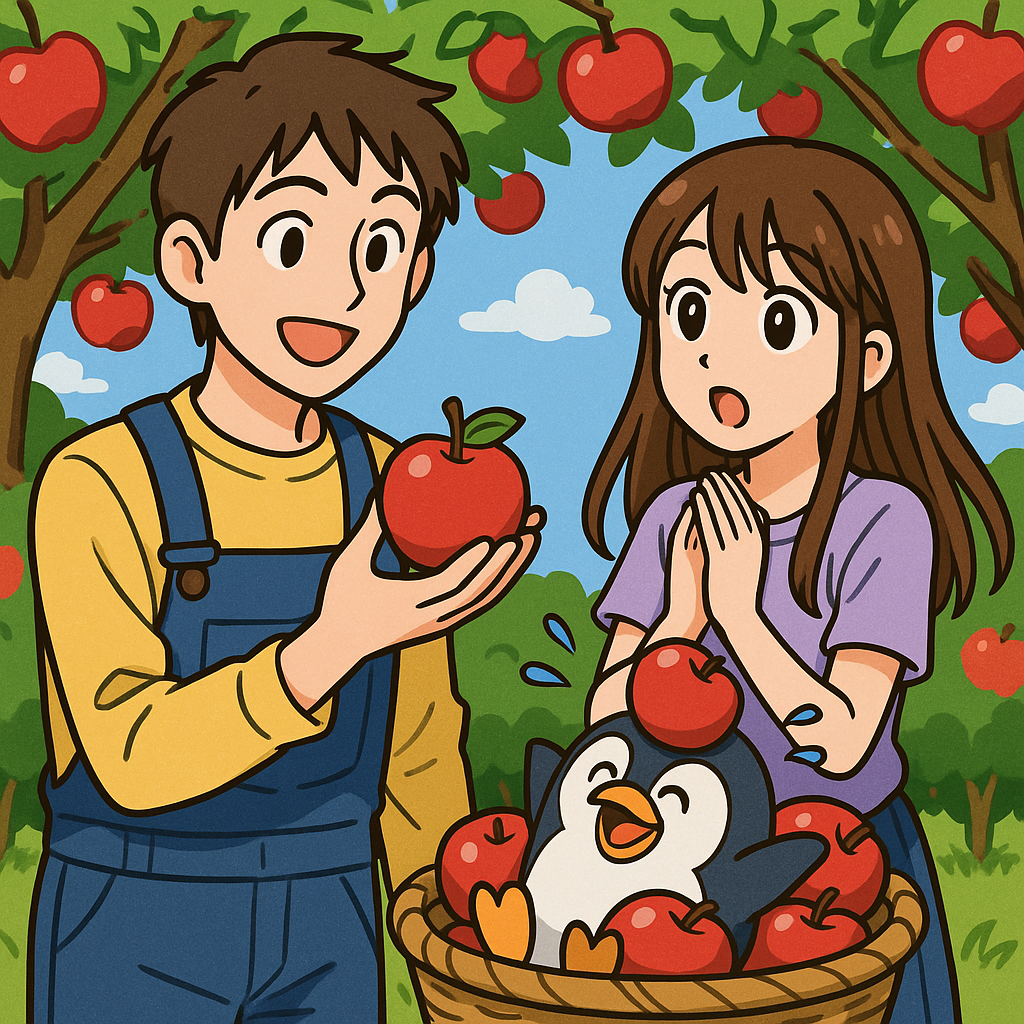




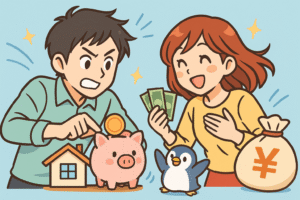


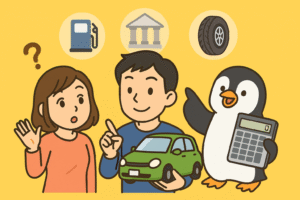
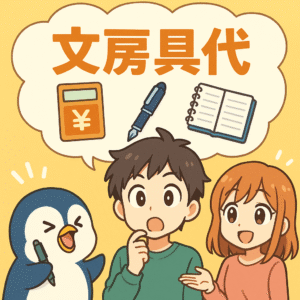

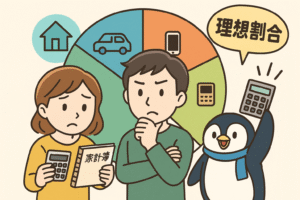

コメント