👨シュンタ「学資保険って、“安心料”を払ってるだけなんじゃないか?」
💁♀️カオリ「でもさ、18歳でまとまったお金が返ってくるって安心感あるじゃん?」
🤖ピー助「“なんとなく安心”と“本当に増える”は別モノでぴ!」
学資保険は「みんな入ってるから安心」という理由で選ばれることが多い仕組み。
でも返戻率は年0.7%前後。物価上昇率2%や投資信託の年4%と比べると、数字のインパクトは歴然です。
さらに、一度契約すると10年以上お金がロックされ、ライフプランの変化や急な出費にも柔軟に対応できません。
安心を買ったつもりが、じつは“将来の選択肢”を狭めているケースも多いのです。
僕たち夫婦も「みんな入ってるから…」と迷いましたが、最終的には入らない選択をしました。
この記事では、なぜそう決めたのか、その理由を本音で解説します。
2025年最新版|学資保険の“おトク”の正体は?
🧔♂️シュンタ「保険会社が“預けた分より多く返しますよ”って言うけど、その間に何してんの?」
🤖ピー助「みんなから集めたお金を運用して、利益の一部だけ返してるんでぴ!」
学資保険の仕組みはシンプル👇
- 毎月払った保険料を、保険会社が株・債券・不動産などで運用
- 利益の一部を「返戻率」という形で還元
- 残りの多くは保険会社の取り分
例えば「10年で8%増える」プランなら、実質の利回りは年0.7%程度。
一方で投資信託(オルカンやS&P500)は年3〜4%が目安。
つまり「安心料」と引き換えに、リターンをかなり低く抑えられているんです。
さらにインフレも問題。
教育費は年1〜2%のペースで上がり続けていて、10年後には10〜20%高くなるのが普通。
それなのに学資保険の返戻率は固定。
「105%返ってきた!」と思ったときには、実質的に物価に追いつけず“目減り”している可能性もあります。
💁♀️カオリ「増えてるつもりが、物価と比べたら“実質マイナス”かもしれないのか…」
🧔♂️シュンタ「そう。表面上の数字に安心してると、インフレでやられる」
🤖ピー助「“安心”の皮をかぶった“低利回りの罠”でぴ!」
わが家が学資保険をやめた4つの理由
💁♀️カオリ「みんな入ってるのに、どうしてやめたんだっけ?」
🧔♂️シュンタ「理由はシンプル。4つある。」
🤖ピー助「“みんな入ってるから安心”って理由で選ぶと、後で後悔するでぴ!」
1. 10年以上お金をロックされるのが不安
教育費って18年先に使うものだけど、実際には家・車・転職など予想外の出費もある。
自由に引き出せない仕組みは、逆にリスクに感じた。
2. リターンが低すぎる
返戻率は105〜110%程度。
10年で+8%=年利0.7%前後。
👉 投資信託(オルカンやS&P500)の3〜4%と比べると、効率の差は歴然。
3. インフレに弱い
契約時に決めた金額が固定だから、物価や教育費の上昇に追いつけない。
「戻ってきた頃には足りないかも?」という不安が残る。
4. 死亡保障は他で備えた方が安い
もしもの保障を含めたいなら、掛け捨ての生命保険で十分。
必要な保障額も安い保険料でカバーできた。
学資保険が合う人・合わない人、わが家の選択肢
✍️
じゃあ「誰にもおすすめできない」というわけではありません。
実際に、こういうタイプの人には学資保険はまだ合っています。
💡 学資保険が向いているのはこんな人
- 投資は怖い・よくわからない → 元本割れの心配がイヤな人
- 強制的に貯金しないと使ってしまう → 仕組み化で安心できる人
- 万一の備えを保険でまとめたい → 「保障+貯蓄」のパッケージを好む人
💁♀️カオリ「“安心料”として割り切れば全然アリだよね」
🤖ピー助「“投資はちょっと無理”って人には、むしろ分かりやすい仕組みでぴ!」
🏠 わが家の準備方法(学資保険ナシ)
- 児童手当+毎月積立をNISAで運用
- 利回り3〜4%想定
- 18年後には500〜800万円規模を目標
- 死亡保障は掛け捨て生命保険でカバー
💁♀️カオリ「“児童手当だけでも300〜400万”って分かると安心だね。そこに毎月積立を足せば、かなり余裕が出る」
👨シュンタ「学資保険との差は歴然だな」
まとめ:学資保険は“安心料”。わが家は別の道を選んだ
✍️
学資保険は「安心をお金で買う仕組み」だと考えています。
わが家は 運用+掛け捨て保険 で十分と判断しましたが、
「投資は怖い」「仕組みがないと貯められない」人には有効な選択肢です。
大事なのは――「なんとなく」で選ばず、仕組みとコストを理解した上で決めること。
💁♀️カオリ「安心料をどう払うかは人それぞれ。うちは別の形にしただけ」
👨シュンタ「“必要ない”と分かったのも、調べて考えたからこそだな」
🤖ピー助「“みんな入ってる”で決めると、親が爆散するでぴ!」
🧭 関連記事はこちら!
🤖ピー助「“学資保険だけ”じゃなくて、教育費や家計全体で考えるのが大事でぴ!」
- 🎓 教育費っていくらかかる?平均額と準備ロードマップ
→ 子ども1人にいくら必要?数字で“正体”を見える化。 - 💵 児童手当って全部使っていい?“ガチ会議”の末に出した答え
→ 我が家が出した“貯める・使う”のリアルな結論。 - 📈 教育費の貯め方・我が家のゆる戦略(児童手当・新NISA・奨学金)
→ 無理せず積み立てるためのシンプルな仕組み作り。 - 🏠 教育資金、家、老後…全部やりたい!我が家の資金配分ルール
→ 優先順位を決めて、予算に“名前”をつける家計設計法。 - 💰 教育資金にNISAはアリ?目的別で積み立てる我が家の考え方
→ 投資と預金を組み合わせた、教育資金のリスク設計。
未来の学費が不安ですか?
我が家の準備法とロードマップをまとめました。
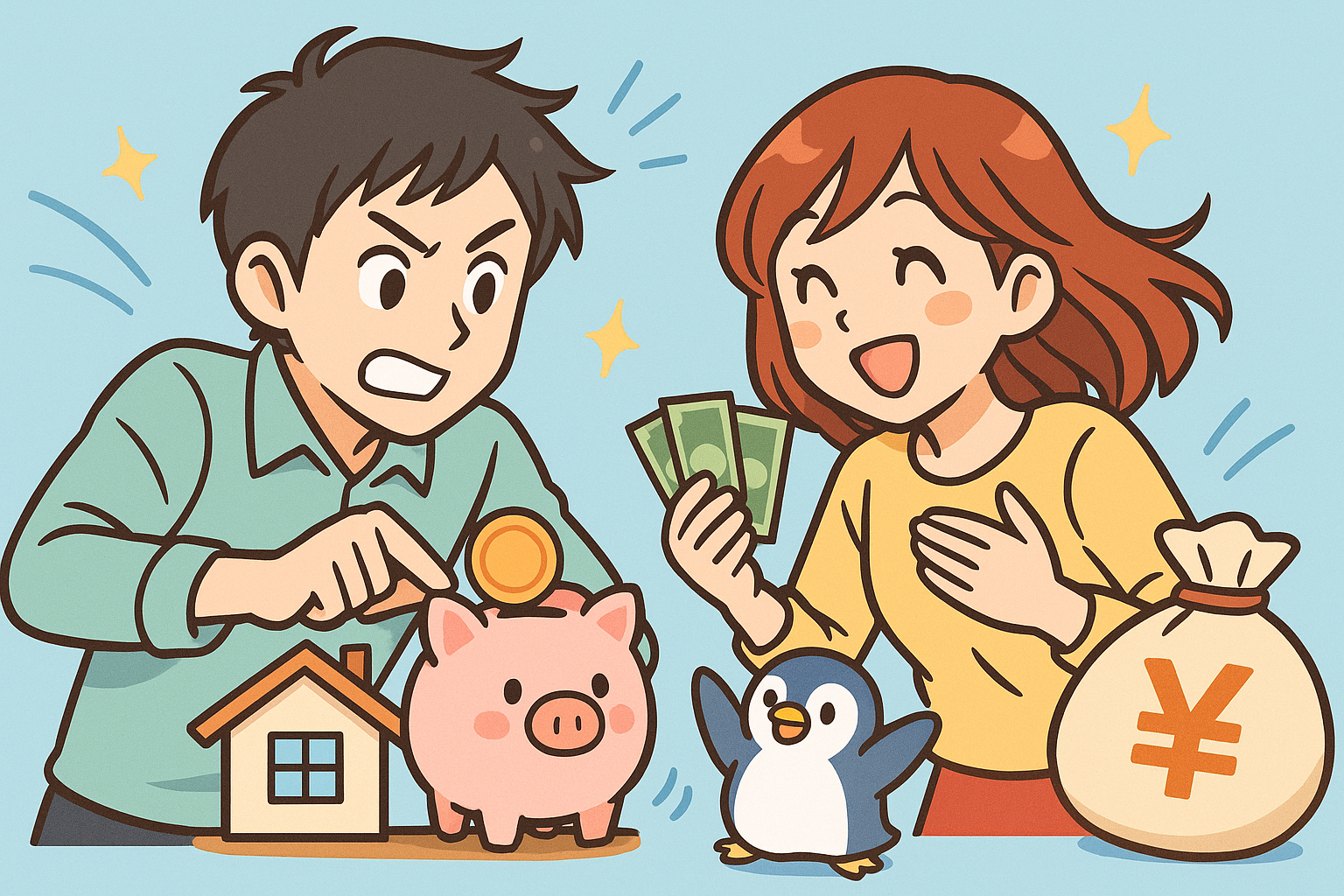






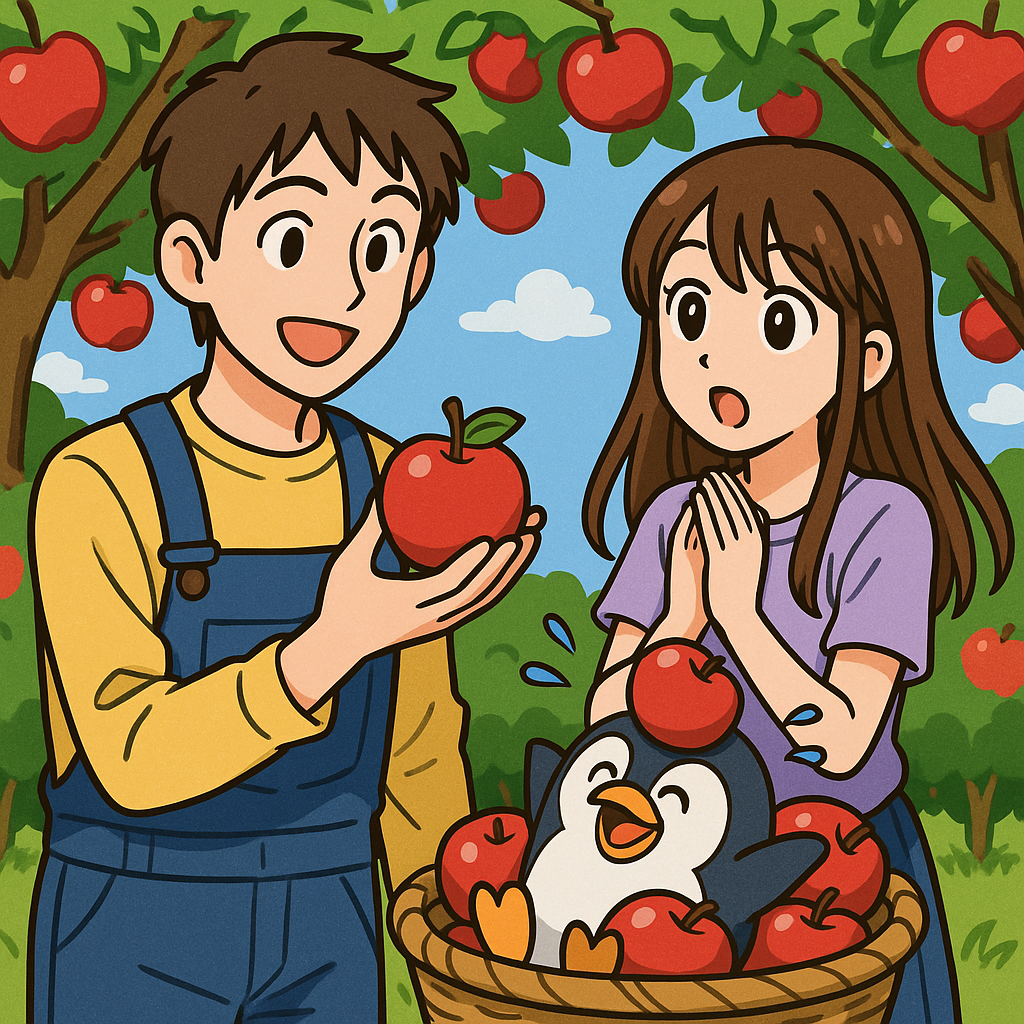




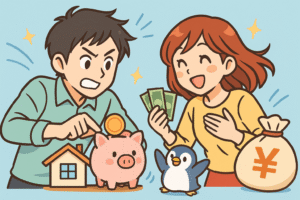


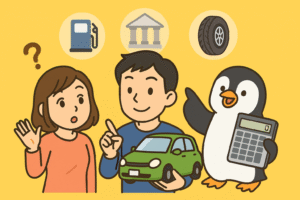
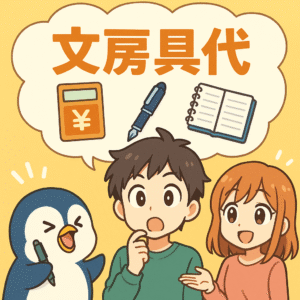

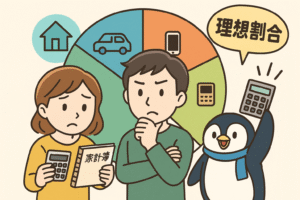

コメント